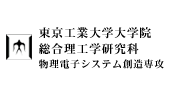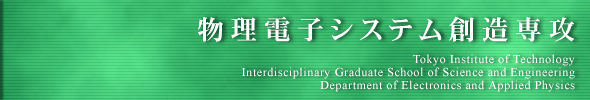|
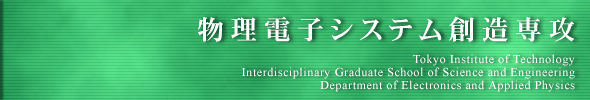 |
| |
|
平成16年度まで密接な連携のもとに運営してまいりました物理情報システム創造専攻と電子機能システム専攻の2専
攻は、平成17年度より改組し、物理電子システム創造専攻と物理情報システム専攻として生まれ変わりました。旧2専
攻では材料・デバイスから情報システムといった電子・情報技術を共に教育研究の対象とし、電気情報系をバックグラウ
ンドとして物理学、化学、応用物理学、機械工学、制御工学、情報工学などの幅広い分野を取り込んだ新しい学問領域を
切り開く専攻として、多くの卒業生を様々な分野に送り出してきました。その成果として近年、人間と情報の関わり合い
を数理・物理的に捕らえる情報システム分野は専門分野として定着し、一方では、ナノテクノロジーといった極微の物質
の究極的性質を駆使して、革新的な情報通信技術の創出を目指す新しい材料・デバイス分野が起こってきました。このよ
うな背景から2専攻を改組して、ナノサイエンス、量子・光技術を含む、先端的な電子情報通信ハードウェア技術を研究
教育分野としてカバーする物理電子システム創造専攻を創設し、新学問分野の創造を目指すことになりました。
新しく生まれ変わった物理電子システム創造専攻は、前身の物理情報システム創造専攻と電子機能システム専攻の「デ
バイス・材料系」教員で構成されています。新専攻では、旧専攻が築いてきた教育研究に関する資産を継承しつつ、情報
技術(IT)分野を支える先端材料、ナノテクノロジー、光デバイス、シリコン集積回路等の最先端材料デバイスの教育研
究を行います。図は新しい物理電子システム創造専攻のコンセプトを示したものです。次世代のIT技術を創り出すために
は、新しい材料の性質とその精密な制御に関する深い物理的理解と最高水準の技術基盤が必要とされるのはもちろん、そ
れらを基礎とした新しいコンセプトに基づく光デバイス、電子デバイス、さらには生体を模したデバイス等の創造が求め
られてきています。さらに、個々のデバイスの機能を相互に連携・融合させ、システムとしての機能を発現させることが
求められています。物理電子システム創造専攻では、IT分野における新材料の創造や新物性の探索、新しい光・電子・生
体に関わるデバイス・システムの開発において、一見多様に見える材料・デバイス分野を互いに“機能融合・集積化”さ
せ、先進情報デバイス・システム分野の創造と教育・研究を推進することを目的としています。
講座や講義構成は、様々な側面から新しいIT分野に取り組むことができる人材を育成することが可能な形になっていま
す。本専攻は、「先端デバイス講座」と「新機能デバイス講座」の2つの基幹講座と、これを支援する5つの協力講座から
成ります。基幹講座の研究室に配属されても、協力講座の研究室に配属されても、学生諸君にとっては同じ条件で、最先
端のテーマによる研究を経験でき、必要な力を身につけることができます。また一方で、技術の細分化・専門化が進行し、
ともすれば全体を見わたすことが難しくなっているにもかかわらず、ハードウェアとソフトウェアの連携もますます重要
になってきています。本専攻では、物理情報システム専攻と、講義や入試をはじめ密接な連携のもとに運営しており、材
料・デバイス分野を中心にすえた上で、情報・システムなど他分野にわたる教育・研究内容を経験することが可能です。

|
|
|
|
|
| |
|